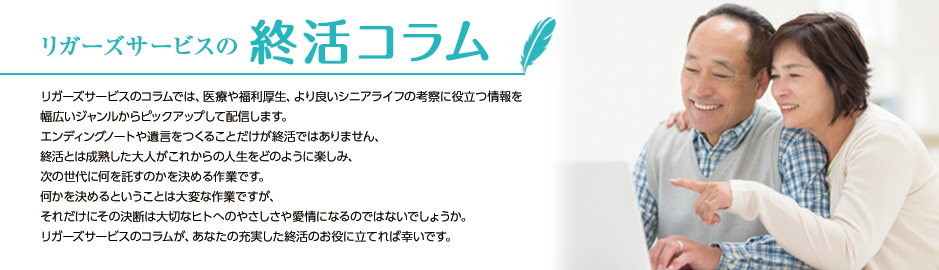終末期や死後の手続き・行事についてなど、人生の終わり方について自分で考え準備する「終活」では、お葬式やお墓の準備だけでなく財産の引き継ぎも重要です。
自分の資産を把握し次世代につなぐ準備は誰にも代行できません。
まずは手持ちの金融資産や不動産をリストアップ、そして必要に応じて集約し、誰にどう残すかを考える…。
今回はそんな「お金の終活」について考えていきます。
■保有財産リストの重要性
保有財産のリストを作る人が増えています。
よく聞くのは親を看取ったときに十分な引き継ぎがなく、預金や株式、保険契約の洗い出しに苦労した経験です。
預貯金では、通帳を探したり心当たりの銀行への問い合わせ。
不動産は、固定資産税支払通知書や親族からの情報をもとに、登記所で登記簿を調べる必要がでてきます。
また相続放棄をしなければ、負の遺産としてあとで相続人が困ることになってしまう借金や連帯保証債務などは、契約書がなければ調査が非常に困難です。
手がかりが少ない中で実際にこれらの調査をするのは、大きなエネルギーとコストがかかるのは安易に予想できます。
そして実際にその問題に直面してしまったのは、札幌市に住む男性Aさん(64)。
「父は2013年に『自宅はおまえにやる』とだけ言い残して亡くなってしまい、他の財産はどこになにがあるか一切分からず、調べるのが大変だった」と振り返ります。
同じ苦労を子どもにさせたくないと、翌年から自分の財産リストを作り始めたAさん。
「預金や株式、保険のほか、世話になった税理士や司法書士の連絡先などいろいろ加えたら、ワード文書で20枚になった」と苦笑します。
横浜市在住のBさん(75)は妻と一緒にエクセルでリストを作りました。
Bさん夫婦は二人で旅行に出かけることが多く、万が一事故に遭ってしまったとき子どもが困らないようにと作ったそうです。
作業を終えてみると「どこにどんな財産があるのかクリアになった。
子どものためだけではなく、夫婦どちらかが先立っても残った方は困らない」とBさんは話します。
紙1枚の簡単な形式でも、問い合わせするすべがあるのとないのでは、その後の手間が大きく違ってきます。
■「資産の終活」ここがポイント
それでは、資産の終活について具体的なポイントを紹介していきます。
まず重要なことは、記入日を書いて定期的に更新することです。
合わせてその存在や保管場所を、家族や信頼できる人に知らせておきましょう。
※リガーズサービスのエンディングノートは2人のバディがエンディングノートの存在を把握しているので安心です。
冒頭のAさんは「家族が集まる正月に毎年更新して、子どもたちに渡して説明したい」と
話します。
Bさんも「プリントアウトして銀行の貸金庫に保管し、そのことを2人の子どもに伝えてある」と言います。
改めて保有する口座やカード類の数が多いと感じる人もいるでしょう。
なんのために口座やカードがあるのか確認し、公共料金や配当金の入金といった目的がなければ解約するのも手です。
不要なカードを減らせれば、年会費を節約できる場合もあります。
ぜひ、リガーズサービスのエンディングノートを活用してください。
残された人たちの不安や苦労を少しでも取り除くために、保有する不動産や金融資産の状態を書き込む項目があります。
ご利用を検討してみてください。


■金融資産はどう整理する?
終活をしていく中で一番気になるのが、自分の財産をどう整理すればいいか?
ということではないでしょうか。
負債も含めた資産に関連することをきちんと整理して残しておくことで、遺される人の負担を大きく軽減することに繋がります。
なかなか骨の折れる作業ですが、少しずつで良いので地道に進めていきましょう。
まず預貯金について、転勤の多かった人は各地で作った口座が休眠状態になっていないかを調べ、不要な口座なら閉じましょう。
ただしキャッシュカードには電子マネーが搭載されて残金があるかもしれないので、はさみを入れる前に確認する必要があります。
株式については、配当金を郵便局の窓口で受け取っている人は、期限切れを避けるため口座への自動入金方式に変えておくと良いでしょう。
単元未満株は相続の移管手続きが面倒なので、証券会社に買い取ってもらうのが無難です。

金融資産をひととおり整理できたら、どの財産を誰にどう渡すか考えなければいけません。
そこで近年の終活人気に乗って増えているのが「遺言代用信託」と呼ばれる金融商品です。
遺言代用信託は、信託銀行等に財産を信託して、生存中は本人のために管理・運用してもらい、亡くなったあとは指定された人に遺産を引き継ぐことができるというものです。
その最大の特徴は、相続人は信託口座から遺産分割協議とは関係なくお金を引き出せることでしょう。
通常は遺産分割協議の後でしか、銀行口座からお金を引き出すことができません。
そのため相続人がたくさんいる場合や、相続配分を巡って揉めている場合はなかなか引き出せず、お葬式代やその他の整理など、亡くなった直後のお金が必要なときに頭をかかえるケースも少なくありません。
しかし遺言代用信託では、遺留分(法定相続人なら必ず請求できる権利)を除くと、遺産分割協議の対象外となり、遺言書の代わりに使うことができます。
そのため指定された相続人は、死後すぐにお金を引き出すことができるのです。
また、元気なうちは預けたお金から決まった金額を年金方式で受け取るなど、その財産を自分のために使うことも可能で、その柔軟性から遺言代用信託の新規受託件数は右肩上がりで増えています。
■遺される家族のためにできること

自分が亡くなったあとに家族に負担がかかることのないよう、自分自身で葬儀の内容や財産の相続など、可能な限り準備を進めておく活動「終活」。
自分がいなくなったあとの準備なので、当初は良いイメージは持たれませんでしたが、最近は就活や婚活と同様に、人生を有意義なものにするための活動と認識されるようになってきました。
また、近年震災や豪雨などの災害が多発しています。
突然の家族の死で悲しみにくれる人々がメディアで取り上げられるたび、自分がいなくなってしまった後のことを意識し、「終活」は誰にとって必要なものであるのかを再認識させられる場面も多くなっています。
自分や家族が安心して「その時」を迎えられるよう、終活という活動を実践しておくことは決して後ろ向きなことではなく、むしろこれからの人生を明るく楽しく過ごしていくための、建設的な行動なのです。
そのための第一歩として、資産のリストアップをはじめてみるのをオススメします。
そして、その際には、書き残したあなたの意思を確実に伝えることができるリガーズサービスのエンディングノートをご利用ください。
終活のためだけではなく、現在の資産状況を再確認できる良い機会にもなるでしょう。
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。