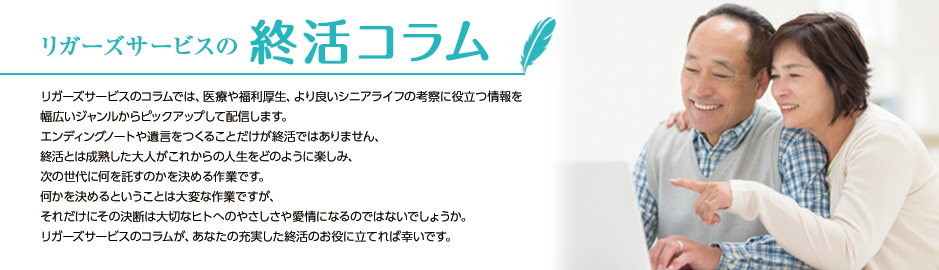前回お話しした今年4月から行われる介護保険制度を根本に置いた介護報酬改定。
それにより、各介護事業所の方針の見直しや、
基本報酬の引き上げ、引き下げなどが行われることになり、
今後のサービスの質向上が見込まれています。
では、利用者側がこの改定でどのような影響を受けるのでしょうか。
今回は、2018年の介護保険制度を利用者からの視点で見て行きましょう。
自己負担が増える?サービスの変化とは
まず介護保険制度を改めて見て行きます。
前回の記事でもご紹介したように、
高齢化社会となった日本では社会保障給付費が予想以上のスピードで増え続けているため、
その給付費を抑える目的から3年ごとに改定案が検討されてきました。
そして今回、2017年5月に介護保険法改正が成立し、
実際に改正が行われるのは本年4月からになります。
では、その改定により利用者には今後どのような影響があるのでしょうか。
利用者に関わる主な4つの改正ポイントを見て行きましょう。
■自己負担額の見直し

これまで自己負担割合が上限2割でしたが、世代間等の公平性を保ち、
2018年8月から一部のサービス利用者の自己負担を3割に引き上げる事になりました。
元々、介護保険制度がスタートした2000年から15年間は原則1割でしたが、
2014年の改正で一定以上の所得のある人が2割負担となり、
今回の改正で2割負担の人のうち「特に所得の高い層」が3割負担に引き上げられます。
この「特に所得の高い層」の具体的な基準は決まっていませんが、
給与収入や事業収入等から、給与所得控除や必要経費を控除した合計所得金額220万円以上の人を指します。
厚生労働省の試算によると、
3割負担の対象者数は、利用者の全体の3%のおよそ12万人になることが分かりました。
さらに、この3割負担導入に先駆けて、
2017年8月から所得区分が「一般」の人の自己負担限度額が引き上げられています。
引き上げられたのは「高額介護サービス費」で、こちらは1ヶ月に支払った利用者負担の合計が上限を超えた場合に超えた分の額が払い戻される制度です。
現在の事故負担上限は月37,200円ですが、
これが月44,400円に上がり、医療保険並の金額に変わります。
ただし、1割負担の人のみの世帯には、年間上限額が446,400円(37,200×12ヶ月)と設定されているので、負担額が増えないように配慮されています。
■福祉用具貸与価格の見直し
2018年10月より福祉用具貸与価格の見直しも行われます。
福祉用具貸与とは、利用者の日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減のために福祉用具を貸し出すサービスです。
これまでは、同じ商品であっても、業者によって仕入れ価格や点検費用等が違うため、
業者により価格に差が出てしまっていました。
そこで今回の改正では、利用者が適正な価格でサービスを受けられるよう貸与価格の見直しが行われます。
レンタル業者に、他の業者との商品価格を比較して利用者に説明をすることが義務づけられることで、結果、適正な価格でレンタルできるようになります。
■介護医療院の新設
今回の改正で4月に新しく介護保険施設「介護医療院」が新設されます。
この介護医療院とは、要介護者を長期にわたって療養するための医療と、日常生活を送る上で必要な介護を一体的に受ける事ができる施設です。
今後も増え続けると懸念されている、要介護者に必要な慢性的な医療や介護のニーズに対応できる施設となっています。
■新しい共生型サービス
介護保険と障害福祉の両制度に新しく「共生型サービス」が位置づけされることになりました。このサービスは、高齢者と障害児者が一緒の事業所でサービスを受けやすくする事を目的としています。
今までは介護保険事業所が障害福祉サービスを提供する場合には、それぞれ指定基準を満たす必要があったため、障害福祉サービスを受けていた利用者が高齢となり、介護保険サービスに変更する際には、事業所を変えなければなりませんでした。
今回の「共生型サービス事業所」では、その手間をなくし、同じ事業所でサービスを一緒に受けられるようになります。
訪問介護、デイサービス、ショートステイなどで、利用者の垣根を越えたサービス体制が実現となりそうです。
これらの4つの改正が主なポイントとなります。
この他にも、
前回ご説明した介護事業所の介護報酬の改定による自己負担額の増加も行われます。
●要介護2の利用者がデイサービスで生活援助を多く利用すると自己負担額が増える。
●看護職員を配置した特別養護老人ホームでは、要介護3の利用者が食堂や浴室等の共有スペースが併設された「ユニット型個室」(定員80名)を利用すると、自己負担額は現状より約800円上がるなど…
事業所の選び方によっては自己負担額が上がってしまう可能性があります。
事業所やサービスを選ぶ際には、
「どこまで自力でできるのか・どこまでできないのか」をしっかりと把握してから、
本当に必要なサービスを選択することが大切となるでしょう。
まとめ

今回の改定では、
自己負担額の引き上げなど少し利用者に対して厳しい内容もありましたが、
新しい介護施設の創設やサービスなど、
今後の長寿社会をより快適に過ごすための改定もされました。
この改定により、今後どのような変化が起こるのか、
実際に利用しながらその動向を観察する必要がありそうです。
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。