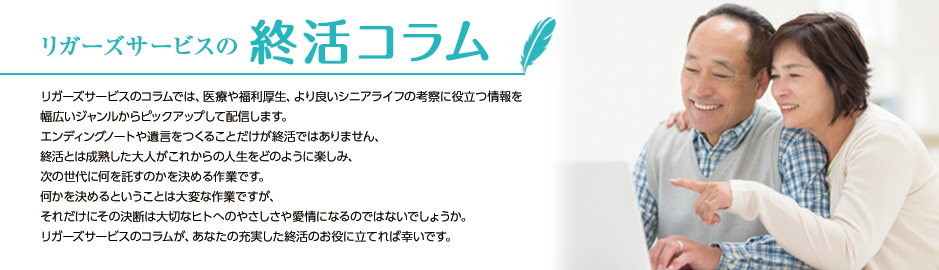障害物をなくし、誰にとっても暮らしやすい生活空間を目指す住宅のバリアフリー化。
特に高齢になると身体機能の低下により歩きや立ち座りはもちろん、トイレなどの室内設備を利用するときなど、日常の動作が負担に感じられたり、転倒など思わぬ事故につながる危険があります。
このため、年齢を重ねても住み慣れた家でいつまでも安心して暮らしていくためには、住宅も高齢者の生活に配慮したものに変えていくこと、住まいの「バリアフリー化」が重要になってきます。
しかし、バリアフリーとひと口にいっても、住宅構造や健康状態、経済状況などによりその形は様々です。
そこで今回は基本的なポイントを参考に、効果的なバリアフリーのリフォームについて詳しく見ていこうと思います。
■住まいのバリアフリー化とは?
高齢による身体機能の低下や障害がある場合、今まで暮らしてきた住宅では日常生活に支障が出るのは避けられません。
例えば家のちょっとした場所、床の段差やトイレ・お風呂などの水まわり、それに階段や廊下など暮らしにくさを感じる障壁=バリアが、高齢者の生活に負担をかけています。
住まいのバリアフリー化とはそんな負担を取り除き、誰にとっても快適で安心な空間を目指します。
国民生活センターによる調査によると、65歳以上の高齢者の事故発生場所は「屋外」より「屋内」の方が多く、さらにその事故のきっかけの半数を占めるのが、「転落・転倒」という調査結果が出されています。
年齢を重ねると足腰が弱くなったり、視力の低下などで少しの段差や引っかかりでつまづきやすくなるのです。



人口動態統計によれば、平成28年に自宅内での転倒や転落によって年間約2700人以上、1日あたり7人以上が亡くなっている計算になります。
死亡にまで至らなくても、骨折など入院となるケースでは完治した後も日常生活の動作レベルが低下しやすくなり、再び歩行が可能となっても、骨折後の痛みや関節の違和感が残ることで動く機会が少なくなってしまいます。
結果的に転倒がきっかけで、寝たきりや生活が不自由になる危険性が高くなるのです。
年齢を重ねても慣れ親しんだ自宅と長く付き合っていくために、一度バリアフリーの視点から家の中を点検してみることをおすすめします。
■バリアフリー リフォームのポイント
工務店に依頼するような大規模な改装から、段差をなくしたり、手すりをつけたり…。
住宅のバリアフリー化には大掛かりな工事が必要になるものから、自分でできるような簡単なものまでさまざまです。
生活する上での問題を可能な限り解消するためには、どのようなリフォームが効果的なのでしょうか?
具体的にみていきたいと思います。
1.段差のない家づくり
一般的にバリアフリーと聞くと、段差のないフラットな作りの床をイメージする人も多いと思います。
実際、移動に支障のない空間にするためには、まず足元のバリアをなくすことが重要です。
健康なうちは分かりにくいのですが、家の中には多くの段差があり、足腰の衰えた高齢者には部屋と廊下のわずかな段差すらも負担になってきます。
たった5ミリ程度の厚みのカーペットや、敷居の小さな段差も危険な場所になりかねません。
敷居を作らずフラットな床にしたり、ミニスロープをつけて段差を解消するほか、床をコルクフロアやクッションフロアにして滑りにくいものに変えることが効果的でしょう。
こうした細やかな配慮や工夫によって車椅子での移動がスムーズになるのはもちろん、家庭内の転倒も防ぐことができます。

2.空間に合わせて「手すり」の調整
どうしても段差が解消できない場所には、手すりを設置しましょう。
歩行が困難な人にとって、階段や廊下を歩くのは大変です。
階段や浴室・トイレなど、足を上げる、しゃがむ、立ち上がる、体の向きを変えるといった動作が必要な場所には、手すりがあると体を支えながら歩くことができますし、途中で休憩したり、さらに転倒を防ぐこともできます。
手すりの位置はその手すりを使う人が使いやすい場所を選び、あちこちにつけるというより、使う人の目線で必要な場所に取り付けましょう。
その際、機能性だけを追求するのではなくインテリアや暮らしを楽しむ気持ちを忘れず、デザイン性のある手すりを選んでみるのもオススメです。

3.車椅子でも暮らしやすく
住み慣れた自宅で暮らし続ける一番のポイントは、車椅子で行き来しやすい動線とゆとりのあるスペースにあるのではないでしょうか。
そのため車椅子での生活を視野に入れてリフォームすることがとても重要になってきます。
廊下が狭く、車椅子走行が困難なため部屋に閉じこもりがち…
といったケースもあるため、車椅子が通行可能な通路幅と方向転換するためのスペースを確保しておくのがベストです。
部屋の出入り口は3枚扉の引き戸にすると開口が広く、車椅子での出入りもスムーズで便利です。
コンセントも車椅子の高さに合わせた位置にあると、ストレスを感じなくてすみます。
さらに外から玄関へのアプローチ部分にスロープや、昇降機などがあれば介助する人も楽になるでしょう。
ただし、これらのリフォームは大掛かりなものになるので、よく検討してから行う必要があります。

■いつまでも住み慣れた家で過ごすために
老化は誰にでも起きる現象で、避けることはできません。
若い頃は何も考えずにできたことが、年齢を重ねると難しく感じてしまうことが増えてきます。
「まだまだ大丈夫!」と油断していると文字通り足元をすくわれ、家の中で思わぬ怪我をしてしまうリスクは年々増えていってしまうのです。
自分の老いを目の当たりにしてしまうのに抵抗があり、バリアフリー化を避ける人もいるかもしれません。
しかし、わずか1センチの段差が死に至る危険な障害になるのなら、それをわざわざ家に残しておく必要性はありません。
将来のための安全対策、そして住み慣れた家にいつまでも安心して快適に住み続けるために、住まいのバリアフリー化を検討してみてはいかがでしょうか?
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。