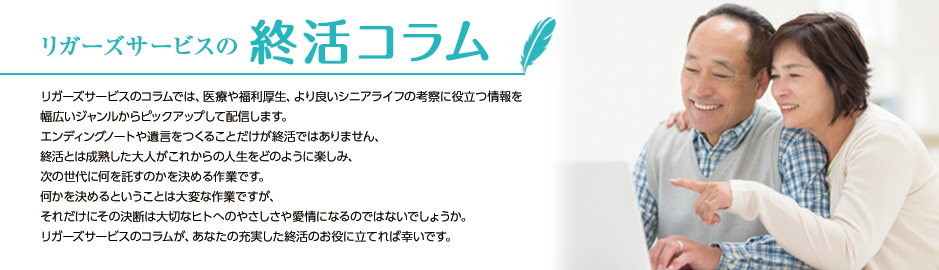誰をどこまで支えるのか。
現在、社会保障制度の根幹である「線引き」を見直す時が来ています。
超高齢化により、医療や介護年金などに必要なお金が増え続け、
これまで当たり前だった支え合いが続けられなくなってしまう危機が訪れています。
社会制度の維持のために、今必要なことは何なのか。
一緒に考えて行きましょう。
75歳まで働ける?高齢者の引き上げによる影響は。
前回の記事で話題にした高齢者の定義を引き上げるという話に連動するのですが、
高齢者の線引きにより、それを支える立場である支え手の人数が大きく変わります。

厚生労働省が発表した「人口動態統計」と「将来推計人口」から計算した表によると、
2000年には65歳以上の高齢者一人につき、
これまで、65歳未満の「現役」3.5人で支えてきましたが、
65歳以上を「高齢者」という定義のままで進んで行くと、
2030年の現役は1.7人と大幅に減少してしまう計算になります。
このままでは高齢者を支えることがとても難しくなってしまうのが現状です。
しかし、この高齢者の線引きを70歳以上にすると現役は2.4人、
さらに75歳以上だと今より少ないですが3.4人で支えるという計算になるそうです。
この人数を見ると、線引きによって高齢者ではなくなった65歳以上の方が、
支え手に回っているのが一目瞭然です。
前回のコラムでもお話しましたが、この高齢者の線引きを変える提言は、
今まで支えられる立場であった高齢者が、
今度は支え手になる時代へと変わる布石となりました。
こうした自らの生活は自らで支える、「自助」が今後必要とされる時代へとなってきています。
しかし、70歳以上の高齢者が本当に働けるか分からないのもまた事実です。
自助を徹底しすぎたために、
誰にも頼れず、知られずに亡くなってしまう孤独死に繋がってしまっては意味がありません。
そこで求められているのが、周りの人と交流や協力によって成り立つ「共助」なのです。
大切なのは地域の人との盛んな交流

共助の仕組みは、
先ほどの「自助」や、行政に頼る「公助」で補えなくなった隙間を埋める、
人々の連帯(Fraternity=連帯、互助、友愛)によって作られます。
少子高齢化社会の現代において、
自助努力や公的な社会保障制度だけであらゆる事情のある生活者全員を支えていくことは困難です。
だからこそ、地域でお互いに助け合っていく共助が重要視されているのです。
人と人との繋がりが希薄となっている現代社会で、
地域の人との交流を行っている人はどれぐらいいるのでしょうか。
表を交えながら地域との付き合いの現状を見て行きましょう。

2017年の高齢社会白書で行われた調査によると、
地域との付き合いを積極的に行っている人は男女合わせて全体の半数いることが分かりました。
近所付き合いの程度では、あいさつから立ち話まで、
女性では相談相手や助け合いの関係を構築している人など多彩な交流を行っています。

さらに自治会、町内会や地域安全などの社会的活動を行っている人に対しての調査では、
活動をして「地域に安心して生活するためのつながりができた」と回答している人が
50.6%もいることが分かりました。
こうした地域との繋がりを持つことにより、
いざという時に支え合える共助の関係を築くことができるのです。
自助や公助が限界を迎える日が近いからこそ、
地域の人たちが協力し会える環境づくりを行っていく必要があるのではないでしょうか。
まとめ
少子高齢化が進んでいる現代、
ご近所との積極的な交流が必要になってきています。
お互いがお互いに声を掛け合い、支え合う共助社会をつくって行くことが、
未来の日本を支えるのに大切なことだと思います。
終活世代の方々で、近所に親しい人がいないと思われている方も、
まずは「向こう三軒両隣」を目標に交流してみてはいかがでしょうか。
終活そのものを仲間と一緒に行い、
お互いに相談したり、報告しあったりするのもいいかも知れませんね。
【関連リンク】
いくつになったら「高齢者」?
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。
【公式ホームページ】あなたの終活に役立つ、リガーズサービス