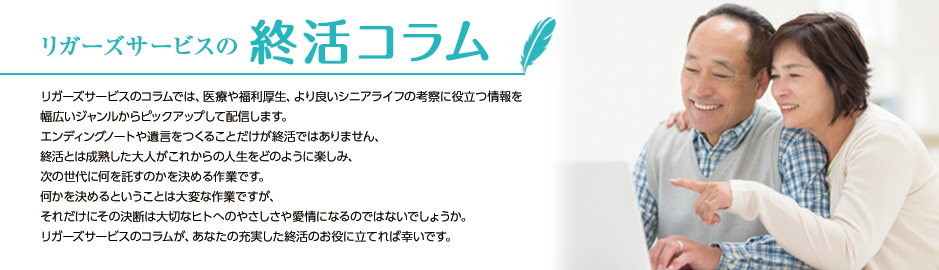大寒波が日本を直撃した2018年。
2月末になろうとしている現在でも、
未だ朝と夜は上着を着ていないと寒い気温です。
そんな冷えた身体を温めるのに、一番に思い浮かべるのはお風呂だと思います。
しっかり湯に肩まで浸かって体の芯から温まる…。
そんな冬のリラックスタイムですが、
お風呂の入り方に気をつけないと、
体調が急変して亡くなる恐れがあることをご存知ですか?
今回、終活世代の方々には要注意である、
寒い夜のお風呂の危険性と対策についてお話します。
増える突然死。浴槽での溺死者数増加。

厚生労働省の人口動態推計によると、
2004年での自宅の浴槽での溺死者は、2,807人でしたが、
2016年には5,138人と1.8倍に増加しています。
そのうち65歳以上が9割、85歳以上が半数を占め高齢者の多さが目立っています。
さらに入浴中の心筋梗塞や脳卒中による死者も含めると、
推計17,000人〜19,000人が毎年亡くなっています。
なぜ、お風呂に入るだけなのに心筋梗塞や脳卒中になってしまうのでしょうか。
その理由には、外気の気温と入浴の仕方にあります。
本当は怖い「ヒートショック」とは?
冷え込んだ夜の脱衣所や浴室で裸になることで体表温が急速に降下。
寒さで血管が収縮することで、
血圧が急上昇し心筋梗塞や脳卒中を招きます。
また、冷えた体で熱い湯に浸かることで血管が拡張し血圧が急降下。
その結果浴槽内で失神し、水没して溺死してしまう恐れがあるのです。
これらの急激な温度差によって、体に及ぼす影響のことを「ヒートショック」と呼びます。
このヒートショックが起こりやすいのが、体の弱い高齢者なのです。
しかし、気をつけなければならないのは高齢者だけではありません。
糖尿病や高血圧等の持病がある人、
コレステロール値が高くメタボリック症候群、あるいはその予備軍の人なども、
急激な血圧の変化でヒートショックになってしまう恐れがあります。
特に中高年の男性はこれらの健康状態であることが多いので要注意です。
晩酌の後お風呂に入ってしまうこともリスクが上がり危険です。
元気だから大丈夫だと思って油断しないことが大切です。
ヒートショックの発生は健康面の問題だけでなく、
住まいの問題から起きることもあります。
例えば、タイル張りで窓のある浴室は熱が逃げやすく、寒くなりやすいです。
築年数の長い家は隙間風が入ったり、壁に断熱材が入っていないことがあります。
こうした住まいでは、常に体が冷えやすく入浴の時に温度差が激しくなる場合があるようです。
ご自宅のお風呂がどういう構造なのか、改めて確認してみるのもよいでしょう。
ヒートショックを事前に防止するには

ヒートショックにならないためには、まず入浴時の温度差をなくすことが大事です。
手軽に取り入れることのできる対策方法を紹介します。
ヒートショック対策方法
1.脱衣所を暖める
脱衣所にファンヒーター等の暖房器具を設置。
裸になったときの急激な寒さを和らげ、血圧の急上昇を防ぎます。
2.湯船のフタを開けておく
入浴の5分前から浴槽のフタを開けておきましょう。
湯気が上がるので浴室全体が温かくなり、
お湯の温度も若干下がるので、お風呂に入った時の温度差を和らげます。
3.シャワーでお湯をはる
湯船のフタを開けておく理由と同じで、お風呂のお湯をシャワーで張るのは大変効果的です。
湯気で浴室が温まる上に、お湯の温度も下がります。
4.熱いお湯に長く浸からない
熱いお湯とは、42℃以上のお湯のことを言います。
長湯してしまうとのぼせてしまい、頭痛や吐き気を引き起こす場合があるので危険です。
特に高齢者は、お湯の温度は41℃以下に設定し、10分程度で上がるようにしましょう。
室内や脱衣所とお風呂の温度差が10℃以上開くとヒートショックのリスクが高まるため、
一般的に41℃なら、10℃以上開く危険が少なくなります。
6.夕食前に入浴する
夕食前に入浴すると、比較的体の疲れが出ていない状態でお風呂に入れます。
食事をすることで血圧が下がりその状態で入浴すると、
ひどい場合は失神する恐れがあるため、
食事を取る前にお風呂に入るか、食後はしばらく休んでから入浴しましょう。
7.高齢者には一番風呂をすすめない
一番風呂は浴室が冷えきっていて、お湯も入れたてで熱いです。
しかし2番目以降なら、
浴室は温まっていますし良い湯加減になるのでヒートショックになりにくいでしょう。
8.浴槽からはゆっくり出ましょう
入浴中はお湯により体に水圧がかかっているので、
その状態から急に立ち上がると、水圧がなくなって圧迫されていた血管が一気に拡張。
結果、脳に行く血液が減り、貧血状態になって一時的な意識障害を引き起こす可能性があります。
こういった症状は大変危険なので、湯船からはゆっくりと出る事を心がけましょう。
以上がヒートショック対策方法です。
その他にもカンタンな対策としては、
浴槽に入る前に手足など体の末端からかけ湯をしてお湯に体を慣らしていくのも効果的です。
まずはすぐにできそうなものからはじめてみてはいかがでしょうか?
まとめ
「世界一の風呂好き」とされる日本人。
温かいお風呂にゆっくり浸かりたいという気持ちがあるのはもちろんだと思います。
毎日安心してお風呂に入るためにも、
今回ご紹介したヒートショック対策をぜひ取り入れてみてください。
健康的な終活ライフが送れるよう、できることからはじめていきましょう。
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、
次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、
あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。