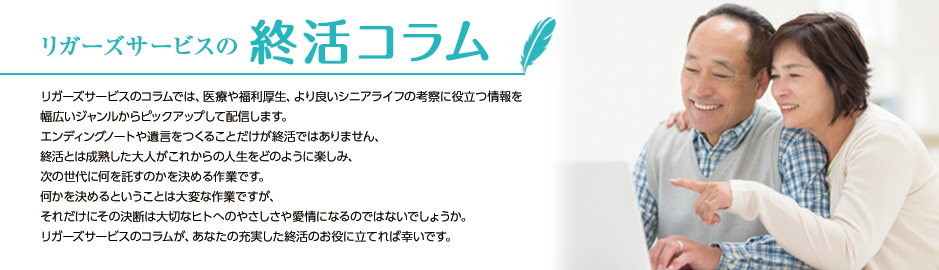前回のコラムでは、65歳以上の高齢者を雇用する企業が増え、働く高齢者が増えていることをお話しました。
その理由は、若い人の人口減少により働き手が減っているだけでなく、元気な高齢者が多く、就労ニーズが高まっていることが挙げられています。
また、高齢者の雇用に対して前向きな企業も増えてきました。
では何故、体も元気で活気のある若い人だけでなく、高齢者も雇用しようと思ったのでしょうか。
それにより、企業側、高齢者側にメリットはあるのでしょうか。
今回はそのメリットについて中心にお話します。
働くことで得られるメリットとは

まずは、働くことで高齢者にどういったメリットがあるのか見て行きましょう。
■収入を得ることができる
前回のコラムでもお話したように、年金が支給されるのは65歳から。
定年退職は60歳からなので、5年間は収入が無い状態になり退職金・貯金で生活をすることになります。
ただ、貯金をどんどん崩していくというのは、徐々に不安を煽るものです。
そういった不安を、働いて収入を得ることにより減らすことができます。
■体が健康になる
働き始めると、規則正しい生活になるので頭を使うようになります。
頭をよく使うことで認知症の予防にもなり、軽い仕事でも作業をすることで程よい運動になるので運動不足が解消されます。
また、雇用形態によっては健康診断を受けることができるので、病気の早期発見にも繋がる可能性があるのです。
■コミュニケーションが取れる
老後生活でこもりきりになると、外部との関係が絶たれてしまい、孤独を感じてしまう方が少なくありません。
しかし仕事をすると、職場のスタッフとコミュニケーションがとれ、接客の仕事だと直にお客様から喜びの声をもらったりと刺激があります。
これにより、仕事をしていることの充実感や、生きていることへの満足感を得ることができるのです。
次に、企業が何を求めて高齢者を雇用しようと考えているのか、企業側が高齢者を雇うメリットを見て行きます。
■真面目に勤務する人が多い
高齢者男性の就業意欲のある人は、60歳から65歳までで50%を超えているとされています。
そして働く姿勢は真面目で、接客態度も良く若手の見本になるなど、企業とお客様から好評価を得ているのです。
職員・店員の好評価は企業への評価につながるので、企業側には大きなメリットになります。
■客層に変化をもたらす
高齢者のスタッフが増えると、同年代の高齢者の来店が増えたというお店が多く見られます。
来店する高齢者のお客様からは、「同世代の人が働いているとお店に入りやすい」「同世代の人が頑張って働いているのを見ると、元気をもらえる」などの声をいただいているようです。
■時間の融通が利く人が多い
定年を過ごす人は時間に余裕がある人が多いため、勤務時間に融通が利きやすいということが挙げられます。
働く人の中には、少しだけ働ければいいという方もいるので、普通だと人を見つけにくい短時間勤務の枠を受け入れてくれる人の割合も、高齢者が高いとされています。
■高齢者の経験と人脈を活かすことができる
多くの人脈を築き、様々な事を現役世代に経験してきた高齢者の知恵や人脈を活用してもらい、新しい事業展開や、新商品の開発を行っている事例もあるそうです。若い人には思いつかない新しいアイディアが出てくることは、企業側にも大きなプラスとなっています。
以上が、高齢者側と企業側が得られるメリットになります。
実際に企業で働く高齢者
企業が高齢者を雇用している事例は前回のセブン-イレブンでも話しましたが、別の企業の実例もあります。
仏壇・仏具等の小売り販売を行っているある企業。こちらでは「高年齢者スポット勤務」を実施しています。
高年齢者スポット勤務とは、平常時に1日4時間の短時間勤務、繁忙期は1日8時間フルタイム勤務と、業務量の変化に合わせて高齢者を活用する取り組みです。
その高年齢者スポット勤務を取り入れることで、通常働いている時間に他の従業員が休憩をとることができるようになりました。
そして、繁忙期に必要な人員の確保もできるようになったのです。
また、高齢者は年配のお客様の気持ちに寄り添った接客ができることから、お客様に安心感を与え、それが信頼に繋がります。
これにより顧客の満足度の向上という大きな成果を得ることができたそうです。
このように高齢者の雇用によって、企業や他の従業員に大きなメリットを与えると同時に、働きたいという高齢者のニーズを満たすこともできるのです。
さらに、高齢者を積極的に雇用する企業に対して厚生労働省は助成金を支給しているので、企業にとっても高齢者を雇用することは大きなプラスとなるでしょう。
まとめ

今後も高齢化・長寿化は続いていくと言われ、少子化になり働く若者が少なくなっていくことが懸念されています。
その中で、働く意欲のある高齢者を積極的に活用していくことは、今後の社会には必要不可欠となるでしょう。
高齢者の方も、もちろん老化により体が思うように動かず働けるかという不安もあるかもしれませんが、高齢者の方には経験という大きな武器があります。
それに、働くことは認知症や病気の予防にも繋がり、さらに人とコミュニケーションが取れ明るく前向きな気持ちにさせてくれます。
行政も、高齢者を積極的に雇用していくための支援策をはじめています。
今後は、高齢者が働きやすくなる制度がさらに整えられていくことでしょう。
働く意欲が残っている終活世代・高齢者の方は、再度働いてみることを前向きに考えてみてはいかがでしょうか。
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。