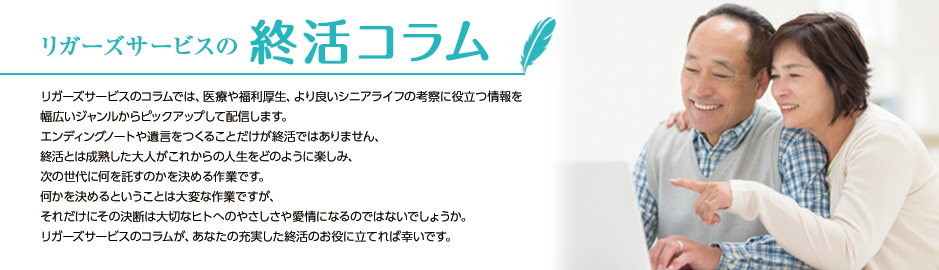「人生100年時代」と呼ばれる超高齢化社会を迎え、シニアを中心に健康を維持する意識が高まっています。今回はそんな健康に力を入れるシニアのお話しをしたいと思います。
■フィットネスクラブの利用増加
健康を維持するために、必要なことの一つに運動があげられます。
そして現在、セカンドライフをより健康的に楽しむために、フィットネスクラブを利用するシニアが増えています。
東京都内にある某フィットネスクラブでは、2016年度の60歳以上の会員数が2012年度から比べると23%も増え、別のフィットネスクラブでも、2016年9月時点で60歳以上の会員数が全体の38%を占めています。
さらに、別のクラブでも70歳以上の会員が2012年は全体の9.7%に対し、2016年では13.5%まで達するなど、ここ5年ほどでどのフィットネスクラブでもシニア会員の増加傾向が続いています。

運動の負担を減らすために難易度を低くしたプログラムでサポートをしてくれるスタッフの常駐や、会員同士のコミュニケーションの場など、フィットネスクラブは運動面以外に、精神面にもメリットがあり、そのことが人気の理由の一つだと考えられます。
■適度な運動で長寿を目指す
フィットネスクラブに通わなくても「適度な運動を行いたい」と思う方も多いと思います。
では「適度な運動」とはどれぐらいの頻度で、どういった運動があげられるでしょうか?
文部科学省の体力・スポーツに関する世論調査(2013年1月)によると、高齢者になるほど「週3日以上(年151日以上)」スポーツを行っている人の割合が高くなっていることがわかっています。

グラフを見てわかるように、60〜69歳では42.4%、70歳以上では53.6%と70歳以上の半分の方が週3日以上スポーツを楽しんでいます。
またあるデータでは、週3日以上運動をすると肥満をはじめとしたメタボリックシンドロームを防ぎ、高血圧や糖尿病などの予防に役立つとされていることから、適度な運動頻度として「週3日以上」があげられます。
では、運動の内容を見てみましょう。

総務省統計局による高齢者調査(2012年9月実施)によると、「ウォーキング・軽い体操」をしている高齢者は38.3%。2006年と比較して約5ポイント上昇していることから、手軽にはじめられるウォーキングが人気なようです。
■運動する上で注意する点
上記であげたように、健康な生活を送るために体を動かすシニアが増えていますが、やはり怖いのは怪我や体調の変化です。
シニアが運動する上で、気持ちと体のズレは注意しなければなりません。
安全で効果的な運動をするための注意点をいくつかあげたいと思います。
まず、運動をするために自分の体調がどのような状態なのか確認してください。
体調の変化は時に目に見えないこともありますので、血圧測定をオススメします。
高齢者に限った話ではありませんが、血圧には絶対除外基準というものがあり、これは最高血圧が180mmHg以上、最低血圧が110mmHg以上の時は運動をしてはいけないというものです。
この状態で運動を行うと、動脈硬化・心臓病・脳卒中といった症状が現れる可能性があるため運動は控えるようにしてください。
【注意点】
①休みを取ること
必要な休みを取らないと、心肺機能や筋力などの運動をつかさどる機能が正しく働かなくなり、心臓に余計 な負担をかけてしまうので注意をしましょう。
②負荷を増やさない
高齢者の場合、負荷を増やす必要はありません。
体力や筋力は年齢を重ねるごとに衰えていくものなので、現状維持することで実際には負荷を増やしてい ることと同じになります。
③水分補給はぬるま湯でする
運動する上で水分補給はとても大切なことですが、冷水は体温が下がったり、胃腸への刺激や負担が大きか ったりするので、15度〜20度ぐらいのぬるま湯で水分補給することをオススメします。
運動を行うことは高齢者にとって筋力の衰えを遅らせるだけでなく、気持ちの衰えも遅らせることができます。しかし、高齢者にとっての運動は体に良いだけではなく、リスクが生じる場合もあるので、正しい知識とゆとりある運動で健康的な体と気持ちを維持していきましょう!
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。