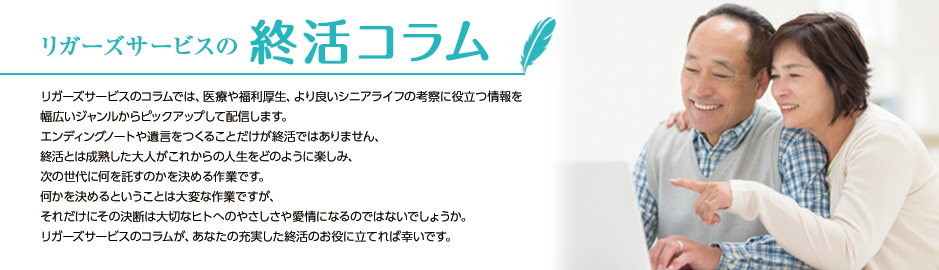普段、「笑うことは健康に良い」と耳にする機会はとても多いと思いますが、
実際にどのように健康に良いのか?、どのような効果があるのか?と考えたことはありますか?
実は、「笑い」と「健康」の関係性は古くから研究が進められており、医学的にも実証されつつあるのです。

普段笑わない高齢者ほど、健康状態が悪い
東京大や千葉大などの研究グループが行った調査によると、
普段笑わないお年寄りは毎日よく笑うお年寄りに比べ、1.5倍以上も「健康状態が悪い」と感じているそうです。
これは全国の65歳以上の高齢者2万人余りを対象に「笑いと健康状態の関係」について調査したもので、
「ほぼ毎日声を出して笑う」と答えた人は男性で38%、女性で48%。
「ほとんど笑うことはない」と答えた人は男性で10%、女性で5%でした。
 出典:2016年2月4日日本経済新聞
出典:2016年2月4日日本経済新聞
そこで笑いの頻度に応じて健康状態を分析した結果、
「ほとんど笑うことはない」人が「健康状態が悪い」と答えた割合は、
「ほぼ毎日声を出して笑う」人と比べ
男性で1.54倍、女性で1.78倍高くなりました。
これまでの調査では、「健康状態が悪い」と答えた人はその後、
寝たきりになる割合や死亡率が高くなるとされています。
笑うと免疫力のバランスを整えることができる
ではなぜ、よく笑う人は健康でいられるのでしょうか。
人間のカラダの中には、ナチュラルキラー(NK)細胞という細胞があり、
この細胞の動きが活発であるほど、がんや感染症を抑えるための免疫力が高まるそうです。
そんなNK細胞の動きを活性化させる要因の一つに「笑い」があります。
人が笑うと脳の前頭葉の動きが活発になり、”善玉”の神経ペプチドが生産されます。
生産された神経ペプチドが体中に流れることでNK細胞に付着、NK細胞を活性化するのです。
逆に、もともと免疫力が高すぎる人は、「笑う」ことでNK細胞の動きが適正値に戻り、
免疫異常の改善にも繋がるとの実験結果も出ています。
笑うことでストレスが解消される
他にも、笑うことで脳内に分泌されるホルモンがあります。
● 鎮痛作用のある「エンドルフィン」
● 嬉しい気持ちになる「ドーパミン」
● 心を穏やかにする「セロトニン」
「笑い」は身体の健康だけではなく、心の健康にも一役買っているのです。
毎日笑って過ごすために

様々な効用がある「笑い」ですが、毎日声をだして大笑いできる日ばかりではありません。
そんな日は、笑えることがなくても笑顔をつくってみましょう。
ふと気付いた瞬間に口角を上げてみる、人と挨拶をする際に微笑んでみる…など、
実は、「作り笑顔」でも脳は笑っていると錯覚するそうです。
「イライラ」や「不安」が人に伝染するように、「笑顔」や「笑い」も伝染します。
人が笑っていると自然と楽しい気持ちになり、誰かが大笑いするとつられて笑ってしまうこともあります。
まずは自分から「笑い」を発信し、自分のまわりの環境もよくしていくことで、
毎日笑って過ごす日々をつくっていけることでしょう。
どうやら「笑う角には福来る」は当たっているようで、終活世代だからこそ笑顔をたやさず過ごすことが健康維持には大切です。
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません、終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。
【公式ホームページ】あなたの終活に役立つ、リガーズサービス