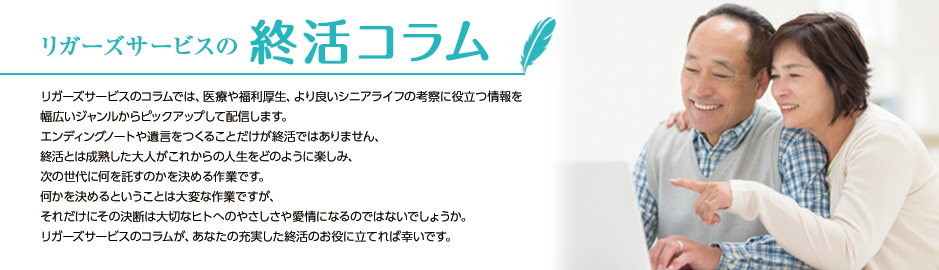ウォーキングは誰もがお金をかけずに始められる簡単な運動の代表です。
中でも、大股で普段より早く足を動かす「速歩」は、通勤や買い物、散歩の際などに手軽にできる健康法です。
「マラソンやジョギングは体力的に自信がない」「運動する時間がない」という人でも無理せず自分のペースで行えます。
また最近の研究で、速歩には足腰の筋力を維持・強化するだけではなく、認知症の予防にも効果がみられることが分かってきました。
普段通りの歩き方に少しだけ負荷をかけることで、効果的に身体や脳を鍛えることができる速歩。
今回は、速歩に適した歩き方とそのメリットについて紹介していきたいと思います。
■ウォーキングで健康維持
年齢を重ねるにつれて、筋肉や体力が低下していくのは仕方がないことです。
何も対策をしなければその衰えを予防することはできません。
そのため簡単に始められてお金もかからないウォーキングはシニアの趣味の代表格にもなっており、年齢別では70歳代が70%以上実施している人気の高い運動です。
体力づくりや健康管理、ストレス発散など取り組む理由はさまざまですが、手軽さに反比例してその効果は絶大です。
なぜならウォーキングは足を使うだけではなく、身体中の筋肉を総動員して行う全身運動だからです。
それでは、ウォーキングには具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか?


■より効果的なウォーキング「速歩」
ウォーキングが健康増進に効果的であることを紹介しましたが、ここからはさらに効率の良い筋力アップにつながる「速歩」を紹介していきます。
速歩とは普段より足を早く動かすことで、普通の歩き方よりも少しだけ身体にかかる負荷を増やす健康法です。
この速歩で重要になってくるのは歩調(テンポ)をあげることではなく歩幅を広くすることだけなので、歩き方の工夫次第で多くの人がすぐに始められる効率的なトレーニング方法になっています。
中高年になると筋肉の衰えに加えて脳機能が歩幅に影響してきます。
専門家によると「横断歩道の白線をまたぐイメージであるくのが理想」とのことで、その歩幅の目標は65センチです。
体格や運動能力などの点で白線を超えるのが難しいと感じる人は、白線は一つの目安と考えても構いません。
ポイントとなるのは姿勢です。
(1)肘は自然に曲げて、腕を後ろに大きく、前は小さく振る
(2)膝を伸ばしてかかとから着地する
(3)おしりの筋肉を持ち上げて背筋を伸ばす
の3点と歩幅が揃えば歩く速度は自然に早くなり、普通のウォーキングに比べて足腰の筋肉が鍛えられます。
さらに視線はなるべく前に保ち、へその下に力を入れましょう。
手をあてて筋肉が硬くなっていればきれいな歩き方になっています。
反対に悪い歩き方は「猫背で視線を下に落とすトボトボ歩き」です。
ビジネス街でよく見かける帰宅途中の疲れた会社員の姿をイメージすると分かりやすいかもしれません。

■大きな歩幅は認知症予防にも
健康寿命を延ばす方法が最近の研究で次々と明らかになってきています。
その中の一つが「歩行の状態が将来の認知症の発症リスクと関連する」というものです。
東京都健康長寿医療センターが高齢者666人を対象に歩行状態を4年間かけて追跡調査したところ、歩幅を「広い」「普通」「狭い」の3グループに分けて調査した結果、「狭い」グループは「広い」に比べて認知機能が低下するリスクが3.39倍も高いことがわかったのです。
女性に限ればそのリスクは5.76倍にも高まります。
その一方、歩くテンポは、「低い」(遅い)は「高い」(速い)に比べて1.01倍と、低下リスクにほとんど差がありませんでした。

なぜ足腰の機能が認知症と関連するのでしょうか?
一見単純そうに見える「歩く」という動作ですが、これには目や足から伝わる情報を瞬時に処理し、次の一歩を踏み出すよう筋肉にシグナルを出すという複雑な処理が行われています。
しかし、認知症になると脳の前頭葉や運動野が萎縮していき、足を前に出そうとするシグナルが脳から筋肉にうまく伝わらなくなるので、自然と歩幅が小さくなります。
そのため、歩幅の狭さは将来的に認知症を発症するリスクが高まっているシグナルだといわれているのです。
日頃から意識して歩幅を広くし、脳への刺激を与えることが認知症予防につながるということになります。
■無理のない範囲で楽しみながら歩きましょう

歩幅を広くした速歩は、慣れるまでは大変かもしれません。
最初はゆっくりでいいので歩幅を広くすることに意識を傾けて歩くのが良いでしょう。
ただし無理は禁物です。
運動のしすぎは逆に免疫力を低下させ病気になりやすくなりますし、強すぎる運動は活性酸素を増やし、身体の老化を進めるといわれます。
正しい姿勢で自分の身体と相談しながら継続して歩くことが大切ですが、他にもウォーキング仲間を作って交流を楽しみながら歩くのも長く続けるコツです。
お金も道具も必要がなく、いつでも始められるウォーキング。
足腰の衰えを予防し健康寿命を延ばすため、さっそく明日から試してみてはいかがでしょうか?
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。