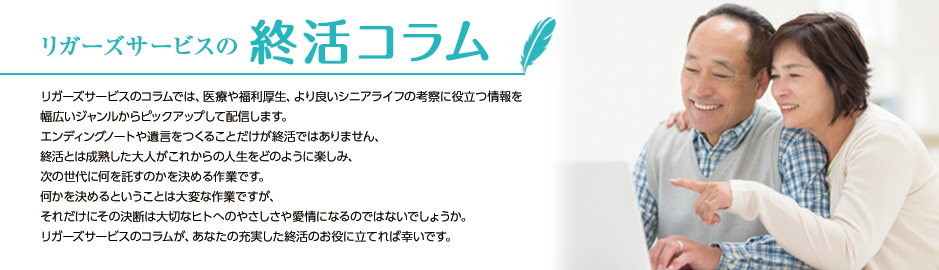手続きが煩雑で、相続関連の手続きの中で後回しにされやすい相続登記。
故人から不動産を相続した場合に行う手続きですが、
法的義務がないため放っておいたり、
うっかり忘れてしまう人も少なくありません。
しかし、放置したがためにトラブルに発展してしまうケースが数多くあります。
期限の制約等はありませんが、
なるべく早めに済ませておいた方が良いようです。
相続登記とは?

相続登記とは、家や土地などの不動産の所有者が亡くなった場合、
不動産の所有権が故人から相続人へと受け継がれたことを明らかにするため、
その名義を相続人に変更する手続きのことです。
不動産以外の預貯金や株式などの債権、
美術品や骨董品等はその対象に含まれません。
そして、いつまでに…という期限があるものではなく、
相続が起こると絶対にしなければならないのかというと、
しなくても法律上は特に問題がありません。
しかし故人名義のままでは、その不動産を売却したり担保に入れることができませんので、
最終的にはその手続きを行うことになるでしょう。
登記放置で親族間トラブル
相続登記を放置するとどのようなトラブルが発生してしまうのか、
もめ事の原因になりやすいケースを見ていきましょう。
50代のAさんは6年前父を亡くし、遺産をどうするか家族で話し合いましたが、
母の面倒をAさんがみるということで家の所有権をAさんが持つことになりました。
家族の仲は良く弟や妹も快く応じてくれたため、
それを書面にすることもなく、相続登記もしていませんでした。
しかし、最近弟が妻と子どもを残し急死してしまい、
先行きに不安を感じた弟の妻がAさんに不動産の分け前を要求してきたのです。
夫の死亡に伴い、Aさんの父の遺産を相続できる立場になった妻子の言い分は法律上正しく、
相続登記を行っていなかったAさんは、
自宅の分割について彼女らと協議しなくてはいけなくなってしまいました。

もしAさんが相続登記を済ませ、所有権が自分に移転済みであることを証明できていれば、
このようなトラブルは起きていませんでした。
相続登記をしなかったために起きるトラブルは、後からでは取り返しがつかない問題に発展することがほとんどです。
そのため、いざというときに不動産の所有権を主張するためにも、相続登記は重要な手続きです。
時間経過で相続人が多数!
上記のトラブル例を紹介したように、不動産の名義人が亡くなると、
名義を書き換えるまでその不動産は事実上、
相続人全員の共有状態になります。
そしてそのうちの誰かが亡くなると、
その所有権は亡くなった人の相続人に相続されます。
そのため、もし相続登記をしないで長期間放置してしまうと、
親族の範囲が広がり権利関係も複雑化してしまいます。
いざ、その不動産を売却できる機会があったとしても、
面識や交流のない相続人だらけになっていると、
その全員の同意を得るのはとても困難でしょう。
他にも相続登記を放置して生じるトラブルはたくさん
■家を売ろうとしたときに契約書を作成できない
■家を担保に借金したくても金融機関が応じてくれない
■他の法定相続人が心変わりして分け前を求めてくる
■年月がたつほど法定相続人が増え、遺産分割協議が困難に
■隣地との境界確定が困難になり相手に迷惑をかける
■故人名義の不動産に、権利がないのに固定資産税を払い続けないといけない
■相続人の中に認知症の人が出てくると、法定後見申立をしないと権利がまとまらなくなる
震災復興を妨げた相続登記の放置
未曾有の被害をだした東日本大震災。
震災の復興の現場でも、相続登記を放置したことによる問題が起きています。
被災地では海に近い低地が甚大な被害にあったため、
仮に再び津波に襲われても大きな被害を出さないよう、
政府は高台への移転事業を進めています。
しかし、そのためにはまず用地買収をしなければいけませんが、
土地の所有者や相続人を探すのが障壁となり思うように進んでいません。
震災発生前に土地の相続登記がされていないのは珍しいことではなく、
24人の共有名義になっていて、子孫をたどると相続人は、
270人にのぼったという事例もあります。
もちろん相続人は被災地の近隣に住んでいるとは限らず、
国内どころか海外在住というケースさえあったそうです。
何代にも渡り相続登記がされていない土地がたくさんあることで、
難航してしまった復興事業。
目先の費用や手間が面倒だからと相続登記を放置することは、
子や孫の世代に迷惑をかけてしまうという事実を認識するべきです。
相続登記はお早めに
このように、相続登記を放置しておくと思わぬトラブルが起こり得ます。
放置は法的には違法なことではありませんが、
後々面倒なことになるのなら早めに済ませた方が良いでしょう。
そのためにも、相続登記には使用できませんが
エンディングノートに自分の資産などの情報を記入しておけば、
こういった問題の時に遺された家族の助けになります。
何より、せっかく故人が築き上げた資産を、
手続きの放置で凍結させるリスクにさらすのは、
なんだか心苦しい気持ちになってしまいます。
終活の基本は、どんなことでも先送りにしないこと。
目をそらさないで、
問題と向き合いましょう。
そう考えると、相続登記は亡くなった方への供養のひとつになるのかもしれません。
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません、
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。
【公式ホームページ】あなたの終活に役立つ、リガーズサービス