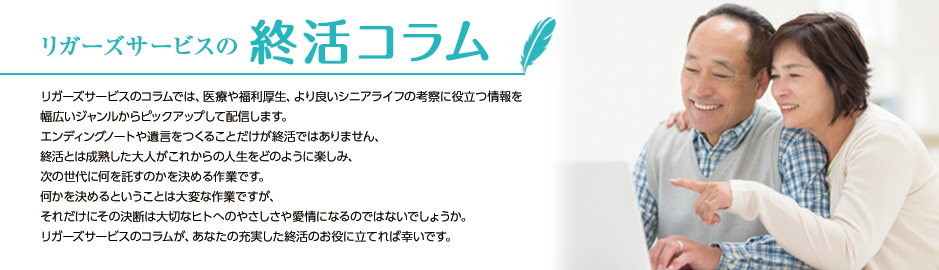高齢になってくると体力の低下などにより、若いころは普通に生活していた自宅に徐々に住み辛さを感じてくる人が多いようです。
ちょっとした段差や、傾斜のきつい階段、寒い浴室など高齢者にとって、
転倒やヒートショックなど怪我のリスクや命に関わる危険なポイントもたくさん…。
それでも老人ホームなどより住み慣れた自宅に住み続けたいという声は多く、
自宅のリフォームを検討しているという方もおられるでしょう。
でも費用やどこを工事したらいいのかなど、よく分からないことが多いのも事実。
そこで今回は、安心していつまでも快適に過ごせる住まいのために、
終活の準備として賢くおトクなリフォーム実現のポイントを紹介していきます。
意外に多い、高齢者の家庭内事故
65歳以上の方の事故の6割が、家庭内でおきていることをご存知ですか?
事故というと交通事故をイメージすることが多いと思いますが、
意外にも高齢者の事故は住み慣れていたはずの自宅で多く起こっています。
畳のヘリなど何気ない段差につまづき転倒したり、階段からの転落など、
事故の多くが「ころぶ」ことに集中しているのが高齢者の家庭内事故の特徴です。

リフォームは元気なうちに
リフォームは実際に怪我をしてしまってから始めるのでは遅いかもしれません。
施工にはある程度の準備期間や施工期間が必要になり、
工事中は仮の住まいで2~3ヶ月暮らすこともできます。
足腰がつらくなってきてからでは負担が大きいでしょう。
老後に備えたリフォームは、不便を感じるようになってからではなく、
少し早いかな?と思う終活スタート世代の50代~60代初めがちょうどいい時期と言われています。
体力もあり、リフォームに必要な時間や労力があることに加え、
資金面でも有利になってくるからです。
60代までにリフォーム資金を準備するのか、それとも退職金を利用するのかなど、
収入源が年金だけになる前に計画しておけばマネープランが立てやすくなるでしょう。
ただし要支援、要介護と認定されている場合は介護保険制度を利用することができるので、
20万円を限度としてその費用の9割を支給してくれます。
手すりの設置や段差の解消などできる工事は限られますが、
自己負担はかなり減るのでチェックしてみてください。
リフォームをお得にする4つのポイント
リフォームしたいけど、実際にどのくらい費用がかかるのかよく分からない…という人は多いと思います。どんな工事でどのくらいかかるのか?費用をできるだけ抑えるコツは?優良業者の探し方は?…など、
ここからはリフォームについての気になるポイントを紹介していきます。
■ポイント1.相場を知ろう
リフォームはすべて「オーダーメイド」であり「定価」がないものです。
希望する工事内容によって、その金額は大きく変わってきます。
とはいえ相場はあるので、あらかじめ知った上で業者に見積もりをとってみましょう。
| 部位 | 中心価格帯 | 目安 | |
| 水回り | キッチン | 100〜150万円 | 50〜200万円 |
| 風呂 | 50〜100万円 | 50〜150万円 | |
| トイレ | 〜50万円 | 〜50万円 | |
| 洗面 | |||
| 居室 | リビング | 100〜150万円 | 〜200万円 |
| 外回り | 外壁 | 100〜150万円 | 50〜150万円 |
| 屋根 | 50〜100万円 | 〜100万円 | |
| その他 | 二世帯 | 200〜300万円 | 100〜400万円 |
| バリアフリー | 100〜200万円 | 〜200万円 | |
おすすめは絞り込んだ2~3社に相見積もりをとること。
1社だけの見積もりだと判断がしにくいので、
複数の業者に見積もりを依頼し具合的な適正価格を探りましょう。
その際に、同じ工事内容でも会社によって見積書の書き方が違うことがあるため、
内訳を知りたかったのに合計金額の比較しかできなかった…というケースをよく聞きます。
相見積もりであることは隠す必要はありませんので、
各社に見積もりの形式を合わせてもらうと比較がしやすくなるでしょう。
■ポイント2.追加工事を発生させない
部材や設備の変更、または施主と業者の間の工事範囲の思い違いなどから追加工事が発生し、
別途費用が必要になることがあります。
「これくらいは見積もりの中に含まれているだろう…」「これはサービスだと思っていた…」など、
有償か無償かを曖昧なままに工事を進めていくと、最終的に驚くほどの追加金額になることも…。
こうした追加工事を発生させないために、見積もり依頼時には要望をしっかり伝え、
プラン作成の段階でじっくりと内容を検討・精査していくことが重要です。
ただ工事が進むにつれて、土台の腐食など見積もり時には分からなかった不具合が明らかになる場合もあります。そのため予算は見積もりの1~2割程度の余裕をもっておくと安心です。
もしくは、経験豊富な業者なら事前調査で見えない部分の追加工事のだいたいの予測はできていますので、見積もり時に「どのような追加工事が発生する可能性があるか」を聞いておくのも予算の計画を立てる上で有効でしょう。
■ポイント3.優遇制度を賢く利用
リフォームは国からのお得な優遇制度が適用されるのもポイントです。
お金やポイントがもらえる補助金タイプや、減税などの公的な優遇制度と、その種類はさまざま。
減税対象のリフォームは「バリアフリー」「省エネ」「耐震」「三世代同居」に関する4種で、
「所得税の控除」や「固定資産税の減額」「贈与税の非課税処置」など優遇措置は数種類あります。
補助金に関しては介護保険制度による「バリアフリー化のリフォーム補助制度」や、
既存住宅の長寿命化を図る「長期優良リフォーム補助制度」、さらには地元の経済活性化を目的とする自治体単位の補助金制度もあり、
適用条件はありますが組み合わせると思っているよりも大きな金額になるかもしれません。
ただし、申請先や期限がそれぞれ違ったり、国の予算がなくなり次第終了してしまう期間限定の補助金制度もありますので、工事着手の前によく確認しましょう。
■ポイント4.ネットで賢く見積もりを取る
たくさんの見積もりをとると、かえって判断に迷ったりすることがあるので、
その際はインターネットリフォーム会社紹介サービスが便利です。
厳選したリフォーム会社を紹介するサイト「ホームプロ」は工事内容や予算を入力すると、条件に合った地元の優良リフォーム会社が複数紹介され各社と商談できるサイトです。
匿名での利用も可能なので気兼ねなくやりとりができます。
どこをどのようにリフォームする?
それでは実際にどこをどのようにリフォームすると、
高齢者にとって安心して快適に過ごせる住環境になるのか考えていきたいと思います。
1.手すりを設置する
手すりは転倒防止に大きく役立つほか、高齢者の自立を促し介護者の負担軽減にもつながってきます。
トイレや玄関、浴室などの立ち座りが必要な場所、階段や廊下など移動の補助として設置しましょう。
2.滑りにくい床に変える
自宅内の事故発生場所として一番多いのは、意外にも「居室」。
最近はフローリングの床が増えていますが、そこでスリッパを履いて歩くことが転倒事故の大きな要因になっています。
タイルカーペットを敷くなどして、転倒しにくい床に変えましょう。
3.照明を変える
高齢になると視力が落ちてしまうので、ちょっとした段差が見えず転倒してしまうこともあります。
一般的に高齢者の住宅では若年層に比べ2~3倍の明るさが必要とされていますが、
常に明るい状態では不快に感じることもあります。
センサー付きライトなど、必要な時に周囲を照らしてくれる設備が良いかもしれません。
4.ベッドを検討する
足腰への負担の面から、高齢になると布団よりベッドの方が寝起きしやすくなります。
ただ、転落の危険もあるので幅にゆとりがあるもの、さらに腰をかけてしっかり足が床につくものを選びましょう。
5.浴室や脱衣所、トイレなどに暖房を設置す
急激な温度変化で、血圧が急変動し引き起こされるヒートショック。
これをなくすためには家の中の温度差をできる限り少なくする必要があります。
冷え込む場所には断熱材や暖房を設置し、身体への負担を軽減しましょう。
6.寝室とトイレが近い間取りにする
高齢になると夜間のトイレ使用頻度が増えるため、寝室とトイレが近い間取りがオススメです。
可能なら寝室に隣接させることで、冷えた廊下を移動しなくてよくなり、ヒートショックを防ぐことができます。
7.室内のドアを引き戸へ
今は大丈夫でもこの先車椅子や杖を利用することになった場合、引き戸だと生活しやすいでしょう。
バリアフリーになるだけでなく、開閉のための面積も小さいので狭い場所からの出入りもスムーズに行えます。
8.キッチンをIHにする
火の消し忘れもありますが、高齢者は視覚機能や運動機能が低下することから、
ガスレンジの使用中に衣服に火が燃え移るなどの火災事故が起こることも…。
その点、火を使わないIHクッキングヒーターなら安心して料理ができます。
百歳まで安心して暮らせる住まいへ
高齢になり体力がなくなったときのことを見据えてのリフォームなら、
50~60代のうちにやっておくのが理想的と言われますが、正直まだまだ必要ないだろう…というのが本音だと思います。
しかし、「車椅子の利用を余儀なくされてから」や「ひざが痛くて移動が困難」など切羽詰まってからのリフォームでは、金銭的にも工事内容的にも時間をかけて考えるのは難しいようです。
トイレはこれ!キッチンはこれ!…と自分で決めないといけないこともたくさんありますが、
高齢になり決断力や判断力が落ちてしまっていれば、どうしても業者任せになり、
自分のライフスタイルに合ったリフォームを実現できていない可能性もあるでしょう。
体力も気力も充実した若いうちのリフォームを終活の準備と捉え、
今の自宅を終の住処にするためのポイントになってくるのかもしれません。
将来の自分のために、後悔しない住まいの準備を整えたいものです。
リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、
次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。
【公式ホームページ】あなたの終活に役立つ、リガーズサービス